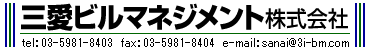★東京・大塚★〜管理・売買・賃貸・コンサルティングなど、不動産に関することは何でもお任せください!〜
2014年04月14日
<No 226>
■マッカーサー道路

3月末、マッカーサー道路と呼ばれる、東京都都市計画道路環状2号線の中での新橋・虎ノ門間の1.4kmが開通しました。
環状2号線は1946年に新橋から神田佐久間町まで延長9.2km、道幅100mの道路として決定されました。当時の連合国総司令部が虎ノ門の米国大使館から東京湾の竹芝桟橋までの軍用道路整備を要求した、などの俗説もあり、そのせいもあってか虎ノ門から新橋までの区間は「マッカーサー道路」と呼ばれました。
虎ノ門ヒルズの開業も今年6月に予定されていますし、活気のある、楽しみなエリアになりそうですね。
※写真は「ケンプラッツ」様より
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20120719/576241/
2014年04月07日
<No 227>
■シェアハウス

最近、某テレビ番組における、男女が1つ屋根の下生活を共に送る、という企画が人気なのもあってかシェアハウスが多方面で話題を呼んでいるそうです。
シェアハウスとは、1つの家を複数の人と共有して暮らすことを指し、ゲストハウスやシェアハウスと呼ばれることもあります。
仕組みとしては、キッチンやリビング、シャワーなどは住人全員で共有し、部屋は一人ずつ個室を利用するというものです。
シェアハウスのメリットとして、敷金礼金、保証人制度がないということです。
賃料も月払いが基本的ですが週払いのところもあり、敷金礼金が不要なので短期滞在の人にも向いている、というようなことが挙げられます。
また、必要最低家具・テレビ・冷蔵庫・エアコン・布団は揃っているところが多く、電子レンジ・洗濯機なども共用スペースに置いてある等、非常に効率的な住まいとなっています。ただ、他人と住むことになるので、ルールをきちんと決めて協調性良く生活することが最低条件になります。
今後も様々なところでシェアハウスが見られそうですね。
2014年04月01日
<No 228>
■桜開花

新しい年度がスタートしました!入学生や新社会人の皆様、おめでとうございます!
環境が一新されると、様々な面で気疲れも多いと思いますが、メリハリをつけた生活を送りたいものですね。
そして、春の風物詩、桜も各地で開花してきました。
都内でのお花見の場所は数多くありますが、私の一押しは目黒川の桜です!大橋から目黒駅付近までおよそ4kmあるのですが、800本以上のソメイヨシノが立ち並んでいます。また、桜祭りなども行われ、町会による甘酒やお餅の提供もある、とのこと。さらに、この目黒川、桜が散ると川が数多くの花びらで鮮やかな桜色に埋め尽くされて、とても素晴らしい風景になります。
ぜひ、この機会に立ち寄ってみてくださいませ。
2014年03月25日
<No 229>
■紙で造る建築


先日、「建築界のノーベル賞」と言われるアメリカの「プリツカー賞」に坂 茂(ばん しげる)さんが選ばれました。
坂さんは、1994年のルワンダにおける民族紛争による大虐殺の際、紙の管を利用した難民シェルターを試作。また、翌1995年の阪神淡路大震災では集会所である「紙の教会」、「紙のログハウス」を作成されるなど、人道的支援から今回に受賞に至ったそうです。
紙管、という日常のどこにでもある素材からシェルター・仮設住宅・ログハウス・教会を造るという発想も素晴らしいのですが、坂さんのインタビューを拝見すると「社会の役に立ちたい」という思いがひしひしと伝わってきます。「木を使いたかったけれど予算がなく、たまたま事務所に転がっていた紙管を使ってみようとした」というエピソードも、普段から真剣に考えて動くことの大切さが反映されていると思います。
※写真は「淵上正幸のアーキテクト訪問記」から転載させて頂いております。
http://www.com-et.com/colonne/002/ban/04.htm
2014年03月18日
<No 230>
■「遺す」ということ

情報雑多な現代社会ではふと、生きることはどういうことなのだろう、と考えます。
様々な答えがあると思いますが、「遺す」ことが最も大切な行為に思います。
命を遺す、資産を遺す、自然を遺す、技術を遺す、思いを遺す…
色々な表現があります。
明治時代の政治家であった後藤新平氏は、
「財を遺すは下、事業を遺すは中、人を遺すは上なり。
されど、財なくんば事業保ち難く、事業なくんば人育ち難し」
という言葉を遺されています。
このフレーズは、社会人として志を持つことの大切さを物語っていながら、同時に自分自身を戒める、自制心を持つことの大切さも表しているように思います。
日々働くことに没頭して精進していく。それが遺すための第一歩なのだ、と改めて感じます。